
子供がピアノを学び始めると、その成長を目の当たりにする親としては、どこかで発表したり、レベルを確認するチャレンジをさせたいと思うものです。
ピアノコンクールはそのための絶好の舞台となります。しかし、多くのコンクールが存在する中で、どのコンクールが子供に適しているのか迷うことも多いでしょう。コンクールに参加することで、小学生の子供たちは目標に向かって努力する経験を積み、自信を深め、また新しい友達を得ることができます。
この記事では、とくに小学生に人気で、初めての参加にもおすすめのピアノコンクール5選をクラシック音楽「ピアノ指導者の竹下忍」監修のもと紹介します。それぞれのコンクールは主催者により、独自の特徴があり、子供の成長を促す素晴らしい機会をつくっています。
ぜひ参考にして、お子さまの個性やレベルに合ったコンクールを選び、素敵なピアノの経験を積ませてあげてください。
【レベル別】小学生に人気のピアノコンクール5選!
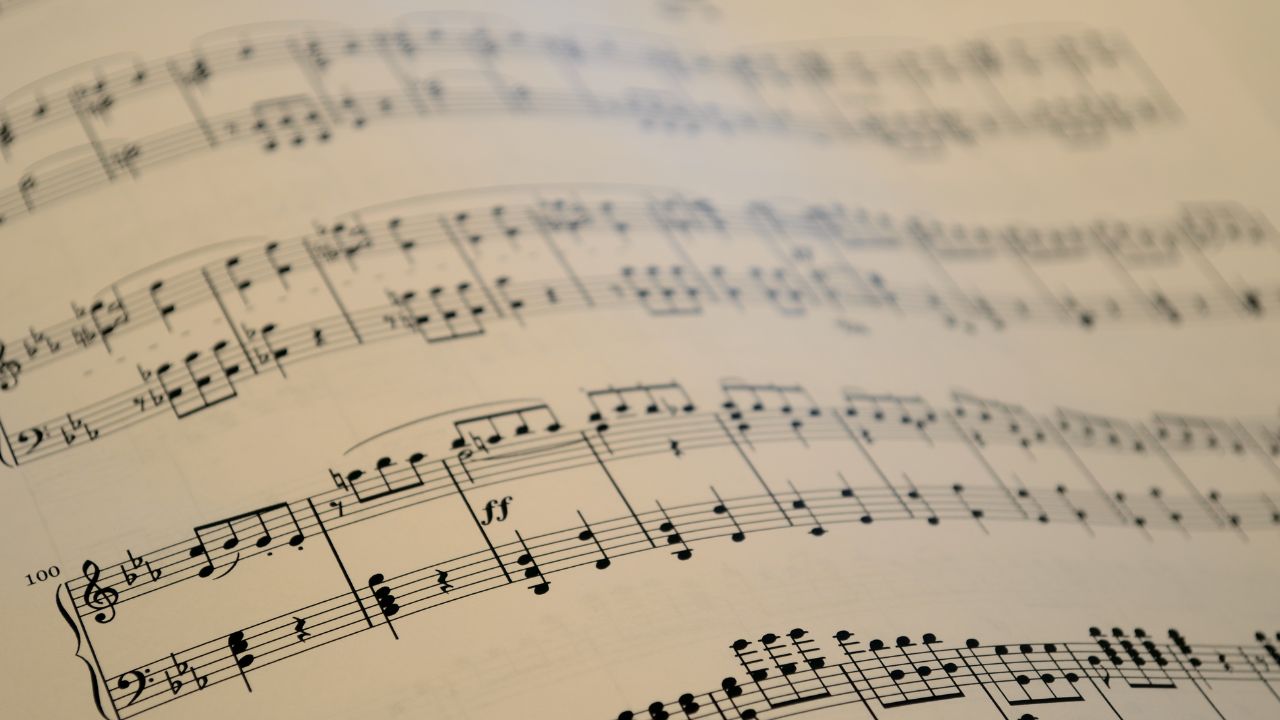
ピアノを習う小学生にとって、コンクールは自身の成長を確認し、さらなる目標を持つ絶好の機会です。お母様方にとって、どのコンクールが子供にとって適切かを知ることは大切でしょう。
ここでは、小学生に人気のあるピアノコンクールを5つご紹介します。それぞれのコンクールは、異なるレベルや課題曲、開催期間、主催者によって特色があります。
子供の成長を促すためにどのコンクールが最適なのかを見極め、彼らの音楽の可能性を広げる手助けとなるでしょう。
では、具体的なコンクールの内容を見ていきましょう。
1.全日本ピアノコンクール
日本のピアノコンクールの中でも、特に歴史があり、全国から多くの才能が集まります。このコンクールは、初級から上級までの幅広いレベルに対応しており、小学生でも気軽に挑戦できるのが特徴です。審査が厳格でありながらも、演奏後には多くのフィードバックを受けられるため、次のステップに進むための貴重な経験となります。
| 項目 | 内容 |
| レベル | 初級から上級まで |
| 課題曲 | 課題曲+自由曲(ブロック大会で演奏した課題曲は全国大会では演奏不可) |
| 開催期間 | 地区大会(~夏)⇒ブロック大会(秋)⇒全国大会(冬) |
| 主催 | 日本音楽協会 |
| 公式HP | https://classicmusic.tokyo/piano/ |
未就学児からプロ・アマチュアの大人まで、幅広い年齢層が参加できるピアノコンクールです。
地区大会は動画審査なので、初めてピアノコンクールに挑戦する小学生も、あまり緊張せず参加できるコンクールです。審査員による細やかなフィードバックも好評です。
2.全国こどもピアノコンクール
全国こどもピアノコンクールは、未就学児~中学3年生まで10部門あるコンクールで、課題曲のみの演奏となるので、初心者にもおすすめのピアノコンクールです。
| 項目 | 内容 |
| レベル | 初級から上級まで |
| 課題曲 | 課題曲 |
| 開催期間 | 地区大会(春~夏)⇒全国大会(夏)全国大会も複数会場から選べる |
| 主催 | 日本音楽協会 |
| 公式HP | https://classicmusic.tokyo/piano/ |
コンクールでの演奏曲が複数あると、1つの曲にさく時間がどうしても少なくなってしまいます。
コンクールを通して、予選・本選と同じ曲を演奏することで、より曲に対しての思いが強まり、1つの曲を深く学べるというメリットがあります。
3.ショパン国際ピアノコンクール in ASIA
ショパン国際ピアノコンクールは、アジア最大級のピアノコンクールで、全国大会を経てアジア各国から優秀な演奏者が集います。小学生部門もあり、日々の練習の成果を試すにはぴったりの大会です。また、ショパンの作品に特化しているため、クラシック音楽が好きな子どもにとって、魅力的な挑戦となります。
| 項目 | 内容 |
| レベル | 初級から上級まで |
| 課題曲 | 課題曲2曲(バッハ1曲/ロマン派1曲) |
| 開催期間 | 地区大会(秋)⇒全国大会(冬)⇒アジア大会(冬) |
| 主催 | ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 組織委員会 |
| 公式HP | https://classicmusic.tokyo/piano/ |
ショパンの作品に特化しているだけではなく、全国大会はホール審査とは別に、オンライン決勝大会にも参加ができる特殊なコンクールです。ホール審査は1曲ですが、オンラインは2曲演奏できるので、色々な曲で力を試したいというお子様におすすめです。
4.ピティナ・ピアノコンペティション
ピティナ・ピアノコンペティションは、コンクールだけではなく、ステップという順位はつかず好評をしてもらえる部門もあり、初心者から音大や演奏家を目指す上級者まで、多くのお子様たちに音楽を楽しみながらステップアップできるコンクールです。
| 項目 | 内容 |
| レベル | 初級から上級まで |
| 課題曲 | 地区予選:課題曲2曲 地区本選(課題曲2曲、但し地区予選とは別曲) 全国大会(予選/本選で演奏した4曲) |
| 開催期間 | 地区大会(春~夏)⇒地区本選(夏)⇒全国大会(夏) |
| 主催 | 一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 |
| 公式HP | https://corporate.piano.or.jp/index.html |
地区予選を突破するには、会場によってはかなりレベルの高いところもあり、ピティナっ子と呼ばれるほど毎年参加をしている子供達も多くいます。初めてのコンクールで心配な方は、ステップを併用してまずは好評をいただくと伊野も1つの手です。また、都内や横浜市などはレベルが高くなりがちなので、他県などでのダブル応募をしているお子様もいます。
5.ブルグミュラーコンクール
ブルグミュラーコンクールは、ブルグミュラーの曲を課題曲中心としたコンクールで、地区大会・地区ファイナルと進んでいきます。幼児~小学生まではA部門・B部門と2つの部門から選べて、4年生までは課題曲にブルグミュラー以外の曲から選曲ができます。
| 項目 | 内容 |
| レベル | 初級から中級まで |
| 課題曲 | 地区予選(小学生5年生~はブルグミュラー練習曲より1曲) |
| 開催期間 | 地区大会(夏~秋)⇒地区ファイナル(秋~冬)地区により異なる |
| 主催 | ブルグミュラーコンクール実行委員会 |
| 公式HP | https://www.burgmuller.org/ |
コンクールに初めて参加するお子様におすすめのコンクールです。ブルグミュラーはピアノを習うお子様たちにとって必ず通る教本の1つです。25曲の練習曲の中でもお子様が好きな曲や得意な曲で勝負できるのも、このコンクールの受けやすさの1つでもあります。
これらのコンクールは、小学生にとって音楽的成長を促し、次のステップに進むための大きなモチベーションとなります。どの大会も異なる特徴があり、参加することで得られる経験は貴重です。コンクールを通じて、演奏技術だけでなく、舞台経験や自己表現力も高めていくことができるので、ぜひ挑戦してみてください!
小学生向けピアノコンクールとは?参加のメリットと挑戦の意義

小学生向けコンクールは、子供たちの才能を発掘し、伸ばす場として注目されています。
予選を勝ち抜いていくことで、自己のスキルを高めることができます。参加者は決められた課題曲を演奏し、審査員による厳正な評価を受けます。ショパンなどのクラシック名曲が課題曲として出題されることもあり、これに取り組むことで演奏技術だけでなく音楽への理解も深まるでしょう。
ここでは、ピアノコンクールに挑戦しようと考えているお子様のお母様に向けて、コンクール参加のメリットや挑戦する基本的な意義について、改めて解説します。
コンクールに参加するメリット
コンクールに参加することは、子供たちにとって多くのメリットがあります。
まず第一に、演奏技術の向上が挙げられます。決められた課題曲を完璧に演奏するためには、日々の練習が欠かせません。こうしたプロセスを通じて、自然と演奏スキルが向上し、音楽に対する理解も深まります。
また、他の参加者との交流を通じて、友人を作り切磋琢磨することで社会性を養うことができます。さらに、大舞台での演奏経験は、自己表現の場として非常に貴重であり、自己肯定感の向上にも繋がります。とくに、予選を突破し、次のステージに進む経験は、大きな達成感を伴い、子供たちの自信を育むでしょう。
このように、コンクールは、演奏技術の向上のみならず、子供たちにとって多角的な成長の機会を提供しているのです。
挑戦の意義
コンクールへの挑戦は、子供たちにとって重要な意義を持ちます。
それは単なる競技ではなく、自己成長のプロセスなのです。課題曲を完璧に演奏するために必要な努力は、自律性と忍耐力を養います。また、ピアノの演奏を通じて、自己表現の方法を学ぶことができるのです。予選を通過し、本選へと進む過程は、失敗を恐れず挑戦する精神を育みます。
さらに、ショパンなどの名曲を演奏することで、時代を超えて愛される音楽の魅力を体感し、文化への理解を深めることができます。とくに、コンクールが子供たちに与える最も大きな意義は、自己の限界を超える挑戦を通して、将来に向けた自信と希望を持つことができる点です。
このように、コンクールは、未来を切り開く力を育む場であり、子供たちにとって貴重な経験となります。
多様な部門とレベルの選択肢
コンクールは、参加者の年齢や技術レベルに応じた多様な部門とレベルが用意されているため、誰もが自分に合った挑戦ができるよう工夫されています。
初心者から上級者までが参加できるように、予選はもちろん本選まで段階的にレベルが設定されています。また、特定の作曲家、たとえばショパンやブルグミュラー、バッハなどの作品だけを演奏する特別なコンクールが設けられることもあり、参加者は自分の興味や得意分野に応じて選ぶことができます。
このような選択肢の多様さは、子供たちが自分の能力を最大限に発揮できる環境を提供し、適切な目標設定を可能にします。さらに、コンクールの期間を通じて、定期的な目標を持つことで計画的な練習が促され、集中力や計画性も養われます。多様な部門とレベルの選択肢は、参加者にとって大きな利点となり、成長の機会を広げています。
子どもに合ったピアノコンクールの選び方のポイント

ピアノコンクールに参加することは、子どもにとって大きな成長の機会となります。しかし、どのレベルのコンクールを選ぶべきか悩む親御さんも多いでしょう。
それぞれのコンクールには異なる特徴や目的があり、子どもに最適なコンクールを選ぶことが重要です。
ここでは、子どもに合ったピアノコンクールの選び方について詳しく解説します。親として、子どもの技術や性格に合ったコンクールを選ぶことで、ピアノ演奏のモチベーションを高め、より良い経験を提供することができます。
お子様の成長を見守りながら、どのような基準でコンクールを選ぶべきか、具体的なポイントを紹介していきます。
演奏技術レベルに応じたコンクールの選択
ピアノコンクールを選ぶ際は、まず子どもの技術レベルを考慮することが大切です。
初心者向けのコンクールから、上級者向けのものまで、多種多様なコンクールが存在します。初心者の場合、基本的なテクニックや表現力を重視するコンクールが適しています。
これにより、無理なく参加でき、自信を持って演奏に臨むことができるでしょう。一方、上級者には高度な技術や独自の解釈が要求されるコンクールが挑戦する価値があります。技術レベルに合ったコンクールを選ぶことは、子どもが成功体験を積むための第一歩となります。
興味と目標に合ったコンクールの選択
コンクールを選ぶ際には、子どもの個人的な興味や将来的な目標も考慮に入れるべきです。たとえば、将来的にプロのピアニストを目指す場合は、規模が大きく、名誉あるコンクールへの参加を目指すことが重要です。
逆に、趣味としてピアノを続けたいという場合には、規模が小さく講評を丁寧にしてくれるコンクールが適しています。子どもの興味や目標に合ったコンクールを選ぶことで、より楽しく、充実した経験が得られるでしょう。
お子様の希望を聞かず、親御さんの希望で難しいコンクールや規模の大きなコンクールに出場させてしまうことで、お子様が精神的に追い詰められてしまい、ピアノが嫌いになってしまうこともあるので注意しましょう。
コンクールの評価基準とフィードバック
コンクールの選択では、評価基準やフィードバックの内容も重要なポイントです。多くのコンクールでは、専門家の審査員が評価を行いますが、その基準が明確であるかどうかを確認しましょう。
評価基準が明確であれば、子どもがどのように努力すれば良いかが分かりやすくなります。また、コンクールによっては、審査員からのフィードバックを受け取ることができる場合があります。
このフィードバックは、子どもの今後の成長にとって非常に大切です。評価基準が明確で、建設的なフィードバックを提供してくれるコンクールを選ぶことで、子どもはスキルを向上させ、次のステップに進むための具体的な指針を得ることができます。
ピアノコンクール課題曲の選曲のポイント

ピアノコンクールは、多くの小学生にとって初めての大舞台であり、音楽的成長の大きなステップとなります。しかしながら、課題曲の選曲は一筋縄ではいかない重要なプロセスです。
正しい選曲は、子供たちがその才能を存分に発揮し、自信を持って演奏できる基盤を築くものです。親として、どのような点を考慮すべきか、どのような選曲が子供に適しているのかを知ることは、子供の成功をサポートするために非常に重要です。
ここでは、小学生のピアノコンクールにおける課題曲選びのポイントを詳しく解説し、親としてのサポートの仕方について考えてみたいと思います。これを読むことで、練習の効果を最大限に引き出し、コンクール本番での成果を高めるためのヒントを得られることでしょう。それでは、選曲の具体的なポイントについて見ていきましょう。
子供の演奏技術に合った課題曲を選ぶ
課題曲を選ぶ際の最も基本的なポイントは、子供の技術レベルに合った曲を選ぶことです。あまりに難しい曲を選んでしまうと、練習の段階で挫折感を味わい、ピアノへの興味を失う原因になりかねません。
一方で、簡単すぎる曲では、成長の機会を逃してしまうこともあります。そのため、現在の技術力を正確に把握し、少しだけ挑戦的な曲を選ぶことが理想的です。
ピアノの先生と相談しながら、子供にとって最適なレベルの曲を見つけることが大切です。また、曲の中で特に難しい部分に焦点を当て、そこを集中的に練習する計画を立てることも有効です。子供が自信を持って演奏できるように、日々の練習をサポートしていきましょう。
表現力を引き出せる課題曲を選ぶ
ピアノコンクールでは、技術だけでなく、表現力も重要な評価ポイントとなります。そのため、子供の感性や個性を活かせる曲を選ぶことが、成功への鍵となります。
子供がその曲を演奏することで、心から楽しむ姿勢が自然に出てくるような曲を選ぶと良いでしょう。
たとえば、物語性のある曲や、感情豊かに表現できる作品は、子供たちの表現力を引き出しやすいです。子供自身がその曲を気に入り、演奏に夢中になれるような選曲を心掛けましょう。
また、曲選びの段階で、子供自身に意見を求めることも大切です。自分が選んだ曲であれば、練習に対するモチベーションも自然と高まります。
音楽の理解を深めるための選曲
選曲は単に演奏する曲を決めるだけでなく、音楽の理解を深める機会でもあります。
課題曲を通じて、作曲者の背景や曲の歴史、曲の持つメッセージを学ぶことで、子供の音楽への理解が一層深まります。たとえば、作曲者の生きた時代背景やその時代の音楽スタイルを学ぶことで、より深く曲に対する理解が得られます。
このような学びは、子供の演奏に説得力を持たせるだけでなく、将来的に音楽を学び続けるための基盤を築くことにもつながります。親としては、子供と一緒にその曲に関連する情報を調べ、話し合う時間を大切にすることで、より深い音楽体験が得られるでしょう。
コンクール参加の準備:練習計画と心構えの作り方

コンクール参加の準備:練習計画と心構えの作り方
ピアノコンクールに参加することは、お子様にとって素晴らしい挑戦であり、成長の機会です。しかし、成功を収めるためには、計画的な練習と心の準備が不可欠です。
ここでは、小学生のお子様がピアノコンクールに参加する際に必要な練習計画の立て方と、心構えをどのように育むかについて詳しく解説します。お子様が音楽の旅路を楽しみながら、自信を持ってステージに立てるよう、お母様がサポートできる具体的な方法を紹介します。
練習計画の立て方
お子様のピアノ練習を効果的に進めるためには、計画的なアプローチが重要です。まず、目標を明確に設定することが大切です。
たとえば、「1日30分ずつ練習する」といった短期的な目標から始めましょう。これにより、達成感を得やすく、モチベーションの維持につながります。
次に、練習の内容を多様化させることも重要です。課題曲でつまずいてしまう箇所の部分練習を、1日10回連続で弾けるよに設定したり、通して弾く練習などをバランスよく組み込みましょう。
さらに、練習時間を一定に保つことで、習慣化を促します。例えば、毎日同じ時間に練習を行うことで、自然と身体が練習に向かうようになります。最後に、練習の進捗を記録することで、達成感を味わい、次の挑戦に向けた意欲を高めることができます。
心構えの育て方
ピアノコンクールに向けた心構えを育てることは、成功への鍵です。まず、ポジティブなマインドセットを形成することが大切です。
お子様が練習や演奏に対して前向きな気持ちを持てるよう、日常生活の中で小さな成功を共有し、褒めてあげましょう。また、失敗を恐れず、挑戦することの大切さを伝えます。失敗は学ぶ機会であり、一歩前進するための大切なステップと位置づけることで、お子様の勇気を引き出します。
さらに、リラクゼーションや深呼吸といったストレス管理のテクニックを教えることで、緊張感を和らげる手助けをします。心の安定を保つために、趣味や遊びの時間を設けることも忘れずに、バランスの取れた生活を送ることが大切です。
コンクール当日に向けた準備
コンクール当日に向けての準備は、事前の練習と心構えと同様に重要です。
まず、演奏する曲のリハーサルを本番さながらに数回行うことをお勧めします。これにより、実際のステージでの流れや感覚を掴むことができます。
次に、演奏当日のスケジュールを一緒に確認し、必要な持ち物をリストアップしておきましょう。服装や楽譜、飲み物など、事前に準備することで、当日の慌ただしさを軽減できます。また、会場までの移動時間やルートも確認しておくと、安心です。
最後に、前日はしっかりと休息を取ることを心がけ、早めに就寝するように促しましょう。お子様がリラックスして演奏に集中できる環境を整えることで、コンクールを楽しむ心の余裕を持たせることができます。
ピアノコンクールでの審査基準とは?予選突破に向けたポイントを徹底解説

ピアノコンクールに初挑戦するお子様を持つお母様にとって、審査基準や予選合格のポイントを知ることは重要です。コンクールは、ピアノの技術や表現力を試す絶好の機会ですが、合格するためには特定の基準をクリアする必要があります。
コンクールにはさまざまな部門があり、レベルに応じた課題曲が設定されます。これにより、演奏者の技量が公平に評価されます。さらに、コンクールの開催期間や主催者によっても審査のポイントは異なります。このような情報を理解し、適切な準備をすることで、予選を突破し、次のステージに進む可能性が高まります。
ここでは、ピアノコンクールの審査基準、予選突破に向けたポイントを詳しく解説します。
審査基準と評価のポイント
ピアノコンクールの審査基準は、技術的な正確さだけでなく、音楽的な表現力も重視されます。演奏中にどれだけ課題曲の意図を理解し、それを表現できるかが評価の対象となります。曲を分析し構成を理解することが大切です。
技術面では、音の正確さやリズムの安定性が求められます。たとえば、ミスのない演奏や正確なテンポの維持は基本です。それだけではなく、演奏者の個性をどのように課題曲に反映させるかも重要です。
また、部門によっては、演奏の際の舞台マナーや表情、姿勢なども審査に影響を与えることがあります。これらの要素をバランスよく取り入れることで、高評価を得ることが可能です。
練習の段階で技術的な練習と感情表現の練習を組み合わせ、お子様が課題曲を深く理解し、感情豊かに演奏できるようサポートすることが大切です。
予選突破に向けた効果的な練習方法
予選を突破するための練習は、計画的かつ効果的であることが求められます。
まず、課題曲の反復練習は基本ですが、ただ繰り返すだけでは効果は薄いです。具体的には、課題曲の構造を理解した上で、曲のフレーズを感じ音楽性豊かな表現力を身につけることが必要です。
次に、演奏の際にどのような感情を表現したいかを考え、それを具体的な音に反映させる練習を行います。また、録音や動画撮影を活用して自分の演奏を客観的に聴き、改善点を見つけることも有効です。
さらに、リハーサルを開くことで、実際のコンクールを想定した緊張感の中で練習することができます。これにより、演奏時の集中力や自信を高めることができるでしょう。適切な練習期間を設け、無理のないスケジュールでお子様をサポートすることが、予選突破への近道です。
コンクールに臨む心構えと準備
ピアノコンクールに挑戦する際の心構えと準備は、演奏の質に大きく影響します。
まず、コンクールの開催情報や主催者の意図をしっかりと理解し、部門ごとの特徴を把握することが重要です。これにより、お子様がどのような基準で審査されるのかを知ることができます。
また、演奏当日に向けては、緊張を和らげるためのメンタルケアも必要です。たとえば、深呼吸やリラクゼーションの方法を取り入れることで、演奏前の不安を軽減することができます。さらに、服装や持ち物の準備も忘れずに行いましょう。これにより、当日に余計な心配をせず、演奏に集中することができます。本番さながら、練習でも本番のドレスを着て練習するのもおすすめです。
そして何よりも、お子様が音楽を楽しむ心を持って演奏に臨むことが、最も大切な心構えです。親子で協力し、楽しいコンクール体験を目指しましょう。
小学生のためのピアノ指導者選びのポイント

ピアノコンクールへの挑戦は、小学生にとって大きなイベントです。お母様としては、お子様が最高の結果を出せるよう、優れたピアノ指導者を見つけたいと思うことでしょう。
コンクールの予選を通過し、より高いレベルでの演奏を実現するためには、指導者選びが非常に重要です。課題曲の選定から、演奏技術の向上、さらにコンクール当日の精神的なサポートまで、指導者の役割は多岐にわたります。
ここでは、ピアノのレベルやコンクールの部門に応じた適切な指導者の見極め方について詳しく解説します。これから始まるコンクールの準備期間を有意義に過ごし、開催される舞台で輝くお子様の姿を応援しましょう。
指導者の経験と実績を確認する
ピアノ指導者を選ぶ際、まず注目すべきはその経験と実績です。とくにコンクールでの指導経験が豊富な指導者は、課題曲の理解や演奏技術の向上において非常に頼りになります。
過去に指導した生徒がどのような成果を上げているか、どの程度のレベルのコンクールで実績を持っているかを確認しましょう。また、指導者自身がピアニストとしての経験を持っている場合、演奏に関する具体的なアドバイスを期待できます。
さらに、コンクールの予選や本選での戦略的なアプローチも指導者の経験に基づいていることが多いため、お子様が安心して挑戦できる環境を整えるためには、この点をしっかりと見極めることが大切です。
指導方法と教育理念を理解する
優れたピアノ指導者を見つけるには、その指導方法と教育理念を理解することも重要です。
指導者がどのように生徒の個性を引き出し、演奏技術を磨いていくのかを知ることで、娘さんに合った指導を受けられるかどうか判断できます。
たとえば、課題曲の進め方や予選に向けた練習計画など、具体的な指導方法を事前に確認しておきましょう。また、生徒の成長を重視し、長期的な視点でサポートしてくれる指導者は、コンクールの結果だけでなく、ピアノを楽しむ心を育むことにも繋がります。
お母様としては、お子様が楽しく学びながら確実にレベルアップできるよう、指導者選びに慎重を期すことが大切です。
指導者とのコミュニケーションを大切にする
最後に、指導者とのコミュニケーションが円滑に行えるかどうかも重要なポイントです。
お子様が安心してレッスンを受け、コンクールに向けた自信を持てるかどうかは、指導者との信頼関係に大きく依存します。指導者がどのように生徒や保護者とコミュニケーションを取るのか、レッスンのフィードバックやコンクールに向けたアドバイスの質などを確認しましょう。
また、指導者が生徒の意見を尊重し、柔軟に対応できるかどうかも大切です。これらの要素を踏まえ、お子様にとって最適な指導者を選ぶことで、コンクールの準備期間を有意義に過ごし、演奏の場で最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートしていきましょう。
小学生ピアノコンクール成功の秘訣

小学生のピアノコンクールは、お子様にとって初めての大きな舞台であり、成長の一端を見せる貴重な機会です。しかし、コンクール当日は緊張感が高まり、思わぬトラブルが発生することも珍しくありません。
とくに、初めてのチャレンジとなる場合は、親としてどのようにサポートすべきか悩まれることでしょう。
ここでは、ピアノコンクール当日に注意すべきポイントを解説し、予選を突破するための心構えをお伝えします。お子様が自信を持って演奏に臨むために必要な準備や、当日のスムーズな進行をサポートする方法を詳しくご紹介します。
服装と持ち物の準備
コンクール当日は、服装や持ち物の準備が非常に重要です。
まず、服装ですが、ピアノコンクールは公式な場であるため、フォーマルな服装を心掛けましょう。お子様の演奏が引き立つように、シンプルでエレガントな服を選ぶことがポイントです。
また、靴は音が大きくならないものを選ぶと良いでしょう。加えて、持ち物も忘れずに準備しましょう。
楽譜はもちろんのこと、電子メトロノーム、予備の楽譜や筆記用具、緊張して手が冷たくなってしまうこともあるので、カイロを持参すると安心です。当日は会場での待ち時間が長引くこともあるため、軽食や飲み物も持参すると良いでしょう。
これらの準備を怠らずに行うことで、当日をスムーズに過ごすことができ、お子様が演奏に集中できる環境を整えることができます。
心の準備とリラックス法
ピアノコンクール当日は、精神的な準備も欠かせません。特に初めてのコンクールに挑戦するお子様にとって、予選での演奏は大きなプレッシャーとなります。
そこで、心の準備として、リラックス法を試してみましょう。まず、深呼吸をすることは、緊張を和らげる効果があります。お子様と一緒に、深呼吸をする練習を事前に行いましょう。
また、コンクール当日は、ポジティブな言葉をかけることで自信を持たせることが大切です。「あなたの演奏は素晴らしい」「自分らしく楽しんで」といった言葉を贈りましょう。さらに、演奏前に好きな音楽を聴いたり、お気に入りの本を読んだりすることで、心を落ち着ける時間を作るのも効果的です。
こうした心の準備を整えることで、お子様が自信を持って課題曲を演奏し、予選を突破する可能性が高まります。
当日のスケジュール管理
ピアノコンクール当日は、スケジュール管理が鍵となります。
事前にコンクールの開催時間や、部門ごとの演奏順を確認し、余裕を持って会場に到着できるよう計画を立てましょう。遅刻してしまうと、お子様の緊張感が高まるだけでなく、予選の進行にも影響を及ぼす可能性があります。会場へのアクセス方法や所要時間を調べ、当日は余裕を持って出発しましょう。
また、待ち時間を有効に使うために、練習の機会を設けることも重要です。小さな鍵盤楽器を持参することで、控室で軽く指を動かし、課題曲の確認をすることができます。当日のスケジュールをしっかりと管理し、お子様が安心して演奏に集中できる環境を整えることが大切です。これにより、初めてのピアノコンクールを成功に導くことができるでしょう。
まとめ

“小学生に人気のピアノコンクール5選!”をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
ピアノコンクールへの参加は、小学生にとって大変貴重な経験となります。音楽的なスキルを磨くだけでなく、自信を深め、達成感を味わう良い機会です。
とくに初めての挑戦は親子ともに不安や期待が入り混じるものですが、慎重に選んだコンクールに参加することで、その経験はより充実したものになるでしょう。
結果に囚われすぎず、プロセスを楽しむことが大切です。どのような結果であっても、努力を続けることで必ず次へと繋がります。
また、お子様の演奏をしっかりと撮影しておくことをおすすめします。後で見返すことで、次にも繋がりますし良き思い出にもなります。
“プロの撮影“では、お子様のピアノコンクールの撮影も全国各地で行なっています。
自分で撮影すると、撮影に熱中するあまり、演奏を客観的に聴くことが難しいので、撮影を検討している親御様はぜひ、ご相談ください。
お子様の初めてのピアノコンクールが、素晴らしい思い出となることを心より願っています。



